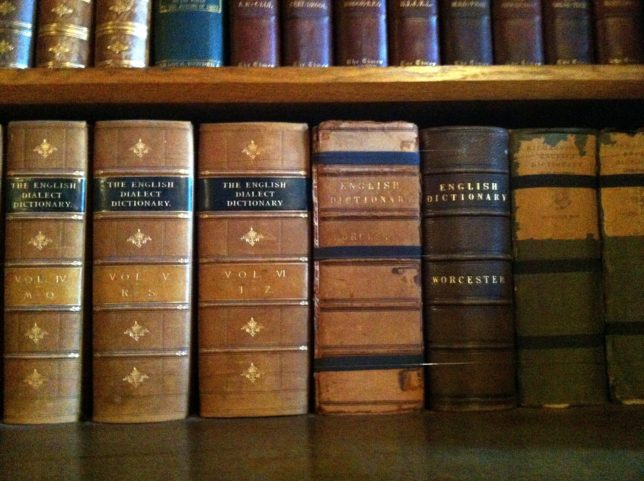言葉(言語)には、母音と子音があります。日本語は母音のみ、もしくは子音と母音の組み合わせで出来ています。ローマ字で書けば、一目瞭然です。
asa (朝)、fuyu(冬)、samui(寒い)、atatakai(暖かい)…全部母音がついています。「ん」は例外ですけど。aoi(青い)は全部母音です。
一方、英語は母音の少ない言葉が多いです。例えば、middle(ミドル)は母音が一個です。カタカナ表記の日本語では母音は3個です。stand (スタンド)も母音が一個。garden(ガーデン)も母音が一個です。トランプ大統領のTrumpも母音が一個。
こうして見ると、英語の母音はかなり少ないことが分かります。
子音が中心となると、言葉を発音するときには子音がきちんと聞こえるように、はっきりと発音しなければ、英語らしくないことになります。~tsのように、「ツ」で終わる場合もよくあります。plantsみたいに。日本語の「ツ」(tsu)で発音すると、母音が入ってしまい英語らしくありません。
英語DJの小林克也さん(声がすごくdeepで、本当にアメリカ人のキャスターのような声をしている)が以前に雑誌に書いていました。英語らしく発音するには、子音を強調しないさい、と。
英語の音読をするとき、子音をはっきり発音して進むと、息を十分吸っておかないと途中で息苦しくなります。hは破裂音なので、一瞬、息がパーッと出ないとダメです。
例えば、heard (hearの過去形) は、hの破裂音がちょっと強く出ないと英語らしくありません。heartもそうです。
英語を話すとき、話す内容に注意が行き発音には意識がほとんど行かないので、発音はできるだけ無意識に出来るようになっていなければなりません。話すときはゆっくりでもいいから子音をはっきり発音した英語で話せるように、日ごろから発音はしっかり練習したいものです。
子音が身につくと英語らしく聞こえ、内容が正確に伝わることになります。
ただ一つ問題は、正確に英語が伝わるようになると英語そのもののアラ(未熟さ)も一層はっきり見えてしまうことにもなります。ある程度英語が話せるようになると、自分の英語が日本語の時のような“知的レベル”を伝えることができずに、相手に幼稚な人間と見えたりすることも起こります(笑)。
カテゴリー: 未分類
日本語と英語の“トーン”の違い
離れた所で話しているアメリカ人らしき男性の声がこちらにもよく聞こえてきた、といった経験はないでしょうか。カフェやレストランだけでなく、通りでそんな声を聞くこともあるでしょう。そんな声を聴いて振り返ってみるとアメリカ人らしき人だったと。人にもよりますが、彼らの声はよく響きます。
私は日本語と英語の“声の響き”について関心があるので、以前から映画やテレビなどでよく観察してきました。また、自分でも多少彼らの英語の声の響きに近づけるようトライしてきて、その経験(体感、フィーリング)から、彼我の差を感じるのです。どうしてそんな違いが出るのか、考えてみました。次の説明は一つの“仮説”(試みの説)です。
日本語は口の中の前の部分で発声(発語)し、英語は口の中の奥の方(喉の方)で発声する、ということだと思います。と書いても、今一つその意味が理解できないかもしれませんが…。ちょっと誤解される言い方ではありますが、「口先発音」と「喉発音」と表現すると私の言いたいことを少し理解してもらえるかもしれません。「口先発音」って好きな表現ではないのですが。
敬語のトーン
日本語には敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語)があります。敬語をしゃべる時、よく注意して自分を観察すると、トーンが高くなっています。気持ちの緊張が姿勢や顔、口に現れ、結果として声が高くなっているのでしょう。会社の新人教育では「社外からのお客様には、トーンを上げた丁寧な声で応対してください」などと教えたりします(私は人事部でした)。
お客様には最大限の丁寧さを示すために、私達日本人は自然に声のトーンを上げて、尊敬・謙譲の意を相手に示すわけです。伝統というか、独特の文化でしょう。
ところで、敬語って日本の歴史の中でいつごろから日本語に出現し、定着したのでしょうか。何故敬語は必要だったのでしょうか。これって、“変な疑問”でしょうか。
リラックスした時のトーン
会社の同僚や部下に話す時には別のトーンがあり、家族間で話す言葉や声にも、更に別なトーンがあります。自分で独り言を言う時のトーンは敬語のトーンとははっきり違います。イライラした時などに発する“怒った声”のトーンもあります。それぞれ、声のトーンは違います。怒った時の声で、特に“ドスを聞かせたような声”は、一番トーンが低いように思います。喉の奥で、喉(声帯、そして仮声帯も)を振動させて発語します。
違うトーンを出せるのは、口の中の発声の位置が違うからだと私は思うのです。 これら色々なシチュエーションで話す日本語も、口の中の前の部分か、中頃で声を作ることがほとんどだと私は感じています。すなわち、口先から、徐々に口の奥(せいぜい中間くらいまで)に移動していくバリエーションです。
口の中の、どの位置で発語するかは、生まれ育って成人になるまで、完全に無意識になっています。
こんな私の話に多少でも疑問を感じる方は、ちょっと注意して自分で観察してみてください。ああそうなのかなあ、と気づくのではないでしょうか。と思います。
「うやまう(敬う)」vs 「へつらう」
「口先で」という表現には、信用できないというマイナスイメージがあります。 「敬う」つもりでトーンを上げていると、いつの間にか「へつらう」声のトーンになっていたりします。「へつらう」は「媚びる」と同じ意味です。トーンは最も高いと思います。「媚びる」とは嫌な言葉ですが、日本語は「媚びる言語だ」と主張する人もいます(嫌ですね、でも一面、真理をついている…?)。
「敬う」が本来の姿勢(態度)だったものが、上の人(上司、お客様、見知らぬ他人など)に対してゴマをする態度に変わり、「口先の」言葉になり、気付かないうちに「媚びる」言葉になっていた…まあ、日常の中であり得ることですね。
発声のメカニズム
声は喉の声帯で声になる、と思っていますが、声帯の声は“原音”で、それを口の中や鼻腔に響かせることによって私たちが聞いている「声」になると言われています。ですから、声帯の振動は声の始まりであって全てではないのです。 声帯は喉頭の中にあり、外から触れるのは喉仏です。言葉を発すると喉仏は少し上に動き、喉の筋肉が緊張状態になります。上がった位置の声帯で緊張した喉で発語すると、口の前部分で声になるときにはトーンが上がるわけです。
喉仏が下がって、しかも喉が緊張してない状態で声を発すれば、トーンは低くなります。独り言を言う時は確かに低くなりますよ。
日本人とアメリカ人の声の重複部分
私の個人的な私見(独断?)では、日本人の「家庭で話す」時の声が、アメリカ人の「やや軽い声」のトーンに近いと思うのです。アメリカ人の“深い声”は、トーンが低く、よく反響している声です。日本人の発声ではめったに見られません。しかし、私たちもイライラして声を荒げて話すときは、アメリカ人の喉発声に近いものと思います。
怒って話すのではなく、心は冷静に、しかし、怒ったときの喉の状態で英語を話すと、アメリカ人と同じベースの英語になる・・・というわけです。難しいですね(笑)。
アメリカ人の“ディープ”な声
アメリカ映画の主人公の声が、日本人にはない“深い声”だと思ったことはありませんか。
Star Wars の第一作目の最初のシーンで、男性のナレーターの声が聞こえてきました。
「遠い昔、遥か彼方の銀河系…( A long time ago in a galaxy far, far away)」という意味の英語のナレーションだったと思うのです。
その声が今でも耳に残っています(たぶんStar Warsだったと思うのですが…)。
引き込まれてしまい、ずっと聴いていたい…とさえ思いました。
最近はインターネットで、アメリカのニュースサイトを頻繁に見ることができます。
キャスターを始め、いろいろな人の声が生で聴けます。バリエーションはありますが、声が印象的な人が少なくないです。
数年前のことですが、そんなニュースサイトでハワイの日系二世らしき若者がとても “ディープ”な英語を話していたのを、今でも覚えています。
ああ、喉や骨格の違いじゃないのだなと思ったものです。
華奢な日本人の骨格だから、ディープな声が出ないと思うのは間違いのようです。
日本人でも低音で、よく響く声の人もいますが、とても少ないように思います。
そして、その“深さ”がアメリカ人ほどではないと感じます。
フランク永井(昭和の流行歌の歌手、「有楽町で逢いましょう」など)のような人は例外的な人ですね。
JALの「ジェットストリーム」という機内クラシック音楽のナレーションをしていた城卓也もよく響く声をしていました。音楽ではなく、声を聴いていたい、とさえ思わせましたね。
日本人のごく一部の人がアメリカ人の低音の声の域にダブっている…と言えるのかもしれません。しかし、一般的に言えば、日本人とアメリカ人の声は、その“深さ”がはっきり違うと思うのです。
昔、中津遼子さん(「英語なんでやるの?」という本を書き、ベストセラーになった)が、日本人の声は遠くまで聞こえない、もっと大きな声で英語を話しなさい、みたいなことを本で主張されていたように思います。
最近は、上川一秋さんという方が、「英語喉」と言う表現を使って、アメリカ人の英語の特徴を説明しています。
ごく最近では、三木雄信さんという方が、「発音じゃなく、発声+リズムが大切」と言い、低い声で、喉の奥を震わせて話すようにと主張されています。
でも、これらの人は本当に少数派です(まったく無視されている、と言ってもいいくらい少数派です)。
日本人が、“ディープ”な声で英語が話せるなら、アメリカ人とのコミュニケーションがより濃密になるかもしれません。肝胆相照らす、みたいな。
英語で外国人と会話する時は、意識して少しでも“ディープ”な声になるよう努めてみてはどうでしょうか?
「緊張して英語をしゃべっているのだから、上ずった声になるのは仕方がない」とは思ってほしくないのです。(上ずった声で英語をしゃべる人は多いですけど。)
でも残念ながら、”ディープ“な声って、意識すればすぐ出せるものではありません。
私自身も何年も意識してきましたが、少しだけ出る程度で自分の夢見る“ディープ”な声にはなっていません。
もっと若い頃にそれを知っていれば…なんて。歳のせいにするな、か。
中国古典の学習方法が今でも生き残っている
日本人の英語ベタは今も変わらないように見えます。
若い世代はこのグローバルな現代、もっと英語がうまくなって当然のはずだよな…と思うのだが、どうやら当然なことにはなっていないらしい。
受験体制がそうさせているのだよ、という人もいれば、学校の先生が文法ばかり言うからダメなんだと主張する人も少なくない。そして、中学では遅すぎるのだ、という意見が強まり、ついに最近小学校から英語学習をスタートすることになりました。
いろいろな主張があり、それぞれに「うん、そうかもしれない」と思わせる説得力は半端ではない。
ところが、誰も言わない理由が別にあると私は思うのです。
はい。話はちょっと長くなりますが、聞いて(読んで)ください(笑)
現在残っている日本の最古の文書は古事記(712年)で、それ以前のものは残っていないそうです。でも、その100年前の聖徳太子(574~622)の頃には既に文字(漢文、漢語)を使っていました。紀元607年、第二回目の遣隋使の聖徳太子の文書「日出ずる処の天子…」は有名です。
中国の皇帝に宛てた手紙で、相手が読める漢文だった、と思います。
一方、仏教が正式に日本にもたらさられたのが、その更に前、紀元538年とされています。その伝来と同時に仏典(多分、すべて漢文。サンスクリット語ではなかったと推測)も多く日本に伝わっていたと思われるので、日本人はそれらを見ていた(読んでいた)はずです。
正式な年号が538年となると、それ以前に既に漢文を読解できた人々がかなりいたと考えるのは自然です。そうでなかったら、仏典などを日本に持ってきても意味がなかっただろうから。
こんな風に考えると、漢文・漢語という中国語が日本にもたらされたのは、大雑把に紀元500年前後(紀元200年代と言う説もあるらしいが)だと想像できます。
ところで、日本の縄文時代、弥生時代には日本には文字がなかったことになっています(「ホツマツタエ」という古代語があったという説はありますが)。
日本に文字がなかった理由について、私は仮説を考えました(検証はできないので、「仮説」とも言えないかもしれませんが)。
それは日本の古代には異民族の支配・被支配の攻防がなかったので、文字の必要性がなかったという仮説です。
言葉の違う異民族が近隣地域に多数存在した場合、支配者は支配を徹底するために言葉を必要としたはずです。
中国大陸のすさまじい支配・被支配の攻防は、まさしく言葉という伝達手段を必要としたと思うのです。
世界最古の文字のひとつ、楔方文字の使用者はフェニキア人だと高校時代に教わりました。
今から5000年くらい前の地中海貿易で栄えた民族です。
詳しくは知りませんが、その後、地中海周辺の民族は多くの文字を発明しました。
文字の発達は、多民族との接触(交易、戦争、支配、被支配などの攻防)がキーだと思うのです。相互に意思を疎通するためには文字が絶対必要だったと。
日本は5000万年前に大陸から徐々に分離し始め、海の中の孤島になったのは1万5千年くらい前です(説によって誤差はありますが)。
1万5千年も隔離されていると、言葉が独自に発展するのも自然なことでしょう。
紀元500年頃、文字のない時代の日本人は中国の文字(漢文、漢語)を知ることになります。
大きなショックを受けたのではないかと想像します。
中国の素晴らしく完成した文字は当時の日本の支配層(天皇を中心とした貴族階級)の知的好奇心を大いに満足させたと思うのです。
そして、支配層のイメージアップに利用できると直感したのではないだろうか。
漢文を学ぶにあたり、中国語の発音を忠実にまねして、中国人と会話しようとしたわけではなかっただろうと想像します。
もちろん言語をそのまま習得して、当時の中国人と会話ができた人もいたとは思います。あるいは通訳(通詞)を専業とする家系の人々がいたかもしれません。
そして日本語訛りの中国語がいつしか漢字の音読みの読み方に定着していったのでしょう。
1500年前から明治まで、日本人はこの漢字(漢語)を高尚な文字、知的レベルの高い人々の文字、学問があることを人々に印象付ける文字として珍重してきました。
途中で、ひらがな、カタカナを発明し、レ点を使わない書き下し文の工夫もしましたが、中心にあったのは、漢文・漢語への憧憬の念でした。
江戸時代は寺子屋でひらがな交じりの漢字を多くの市民が学び、武士は子供のころから論語などの四書五経や朱子学を漢文や書き下し文で学びました。
故に、日本の識字率は非常に高かったと聞きます。
ひたすら漢語の意味を理解することが学問の中心だった時代。
しかし漢語を学んでも、中国人と会話しようとはしなかった時代。
「あの人は学問がある」と言われれば、最高の誉め言葉だった時代は長く続きました。
「学問がある」とは漢文を自由自在に読め、非日常語の漢語が口をついて出てくる人のことだったようです。
ところで、「学問」という英単語はありません。
和英辞典ではlearning, studyとしています。今でいう「勉強」というニュアンスです。
「学問」という言葉から受けるイメージは「勉強」とは違いますよね。
明治になって勉強の対象が漢文から英語になっても、日本人は漢文を勉強してきたやり方をそっくり(?)続けました(一部、例外的な人はいましたが)。
そうです、読んで意味を理解することです。
会話することのニーズはほとんどありませんでしたから、英語も日本語訛りの“音読み”(面白い表現?)でした。
私がここで言いたいポイントは、今の英語の勉強は1500年くらいの漢文学習という長い伝統の上にあるということです。
私達日本人に脈々と受け継がれ、しみ込んでいる学習文化。
だから、日本人なら誰でもスーッと自然に入り込める方法が漢文方式の勉強法だということです。
今でも、日本全国で行われている英語教授法はまさしく漢文式勉強法の流れ(伝統)に沿ったもので、その時々の社会のニーズに影響されて多少の修正が入っても、基本的に長い伝統的な学習方式を踏襲したと言えるのではないかと思うのです。
長い外国語(漢文・漢語)学習の伝統が生き続ける環境で、以前の方法とは違う、会話中心のやり方で英語を勉強しようといっても相当無理があるように思います。
会話中心の学習に変更したいのなら、100%の意識改革、意識転換を図らなければならないでしょう。
英語は学校で勉強する分にはいいが、普段の日常で英語を話すのは恥ずかしい、と言う人さえいます。
日本人の著名人や要人が海外で英語をしゃべっているシーンをテレビでほとんど放映しないのも、英語に対する苦手意識が国民に張り付いているからでしょう。
喋る英語に関しては、いまだに聞きたくない、見たくないとする人々が多いように思うのです。日本人が英語をしゃべっているのを見ると、“こっぱずかしい”みたいに、毛嫌いする人が…
会話を重点とした英語教授を“本気で”推し進めるには、ものすごい覚悟が必要と書きましたが、大げさなことではないのです。
恥ずかしいとか、毛嫌いする心理をまず“消去”しなければなりません。
会話中心の英語学習の推進は“建前の話”としてしか議論されていない、と私には思えて仕方ありません。誰もまじめに、心の底から議論していないと思うのです。
(ちょっと極論過ぎ? うーん…かもね)。
「虫」 insect,bug,wormの鳴き声
もう40年も前の本だが、池田摩耶子という人がアメリカの大学で日本文学を教えていた頃のことを書いています。その中に「虫が鳴く」という表現を教えるのに苦労した経験が載っています。
川端康成の「山の音」と言う小説の中の「八月の十日前だが、虫が鳴いている」という文章は、日本語専攻の学生には文法的には易しいのだが、その意味するところが全く分からないのだという。
「虫が鳴く?何それ?鳴くわけないでしょ!」 アメリカ人の学生は喧々諤々、色々なことを言ったらしい。
池田さんによると、虫= insect, bug, wormとは彼らにとって、「鳴く」存在ではないのだと。
そこで、教室の中で、鈴虫ならリーンリーン、松虫ならチンチロリン、クツワ虫ならガチャガチャ、油蝉ならジージー、くま蝉ならシャーシャー、法師蝉ならオーシーツクツク、オーシーツクツク、などと虫の鳴き声のまねを実演する羽目になり、アメリカ人の学生は大笑いしたらしい。
池田さんによると、ボストンでもケンブリッジでもカリフォルニアのスタンフォード大のキャンパスでも、虫はちゃんと鳴いているのだが、アメリカ人の学生はまったく「聞いていない」のだという。 聞く耳を育てていないとのこと。
「八月の十日前だが」の意味も、何故この文章に入っているのかがわからないらしい。
夏なのに、もう秋を思わせる虫の鳴き声、というニュアンスが全く分からないのだという。
「虫」の声を聞いて、しんみりしたり、悲しくなってしまう感覚は日本人特有のものなのでしょうか。
ところで、「虫」について、日本語ではいろいろな表現があります。
虫のいい selfish
虫の好かぬやつ a disagreeable person
虫の知らせ a hunch
腹の虫が納まらない dissatisfied
本の虫 a bookworm
虫の息 be dying
浮気の虫が起こる have an amorous(多情の)itching
虫が良すぎる asking too much
虫の居所が悪い be in a bad mood
虫も殺さぬ innocent-looking
泣き虫 a crybaby
虫の食った worm-eaten
虫が起こる become petulant
虫がつく have a lover
虫干し airing
虫歯 a bad tooth
虫けら同然 be good-for-nothing
虫眼鏡 magnifying glass
虫酸が走る feel disgusted with
(英語は和英辞書から)
私達日本人は「むし、虫」という言葉について、深く考えることはありません。
これだけ多くの用例があるのですから、「むし」は何か本質的な意味のある言葉なのではないか、と思うのですが、私にはよく分かりません。
少し想像力をたくましくして考えてみると、例えば何千年か前の昔、日本人は「むし」を体の中の一片の“うずき”( “虫酸が走る”、小さな体内の異変)と考えていて、蚊やハエやノミ、その他の小さな生き物は個別の名前で表現し、「虫」を「むし」という言葉では表現していなかった。
そして1500年前頃、中国から漢字が入ってきて、「虫」と言う言葉を知り、それまで個別に言っていた小さな生き物をすべて「虫」と分類するのだと知り、「むし」と同じ音をあてはめた。
それ以来、それらの小さな生物を「虫・むし」と言い続けた(?)
私は「むし」と「虫」とは違うのではないか…と思ったりします(笑)
いずれにしても、「虫」も「むし」も日本人にとって、遥かな昔からとても大切なものなのでしょう。
「質問=恥」ではない英語文化
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という諺がある。
日本では質問することは自分の無知をさらけ出すことになり、恥とされる。
分からないまま過ごすと“一生の恥”だとは思っているが、聞くのはやっぱり勇気が必要。何故って、恥だと思うから。
私達日本人は「質問する=恥をさらす」と思っているらしい。
会社の会議で、上司が指示を出す。部下はただ聞いてその場をやり過ごす。
もし分からなければ、後で他の同僚に「あれってなんのこと?」と聞いて確認するが、その同僚も分からないことがある。
別の同僚に聞くと「多分こういうことだと思うよ」と言って、解説してくれる。
長いキャリアの人は、部内の事情から推察して多分こういうことだと推測してくれるわけである。
時には誰も分からず「それって大して重要なことじゃないからいいんじゃない?」という結論になったりする。
アメリカ人が主催する会議では、Any questions? と言って会議を締めくくる。
そんな時、何も質問がないと答えると「こいつ、関心がないんだな」と勘ぐられてしまう。
だから、間髪を入れずシンプルな質問をすることが好ましい。
アメリカの大学の授業では、質問をすることが成績評価にも影響する。
私が留学していた約60年前も、10年前の遊学の時も全く変わらなかった。
質問することはいいことなのだ。
日本では立派な質問だけは質問していいが、シンプルなくだらない質問をしたりすると、会社内の評価を下げてしまうし、質問された上司が怒ったりする。
また、日本では「質問すること」は暗に反対、賛成できないというニュアンスを伝えることもあるので、質問しただけで嫌われてしまうことも多い。
一般に会話の中で「どうして?」と聞くことは稀だし、また聞いてもなんとなく無視されてしまうことが多い。意識的に無視するのではなく、ほとんど無意識の無視である。
「どうして?」と言う質問に、「どうしてなんでしょうねぇ…そうですよねぇ…」と言いながら、答えもせずそのまま話が進んでいく。
人の言わんとすることくらい察してよ、と言うのが日本人の感覚なのであろう。
「気」と「こころ」
何気なく使っている英語と日本語の対比で、かなりの“ずれ”があることに気づかされることがあります。
例えば、「おはよう」という日本語は英語でgood morningです。 日本語は「早い、遅い」の意味が内包されており、good morningは「いい、悪い」を暗示しています。
ほとんど疑問に思わず同じものだと思って使っていますが、文化的に大きな違いが含まれているように思います。
日本人は何千年もの稲作の歴史から、朝早く作業を開始することが必要だったのでしょう。
一方、good morning, good afternoon, good nightの国では、神の規範に照らして、いいか悪いかだったのではないでしょうか(たぶん)。
まだ時々日中でも寒いことがありますが、英語のcoldと言う言葉は「寒い」だけでなく、水がつめたい、ビールがひえた、気持ちがさめた、態度がよそよそしい、人が冷淡など、いろいろなシチュエーションに使える言葉です。
coldという言葉にそれらすべての意味が混然一体となって内包していると言えます。
言葉の意味の“広がり”でしょう。
一方、日本語の「冷たい」と「寒い」とは違う言葉です。
「今日は寒いですね」を「今日は冷たいですね」とは言いません。「このビール、寒いですね」とも言いません。
でも、英語はcold なんです。
日本語にも大きな広がりを持つ言葉があります。
例を挙げると、「気」です。
「気をつける」を英語に直すと、take care of とかpay attention to(和英辞典)になります。「気を失う」はfaintとか lose one’s consciousnessの訳が出てきます。
「気」に付いて、普段よく使う言葉を列挙してみます。
気がある
気が知れない
気が合う
気が小さい
気が散る
気がふさぐ
気が引ける
気が変わる
気が気でない
気が利く
気がくじける
気が長い
気が乗る
気が抜ける
気が大きい
気が楽になる
気が進む
気が立つ
気が遠くなる
気が付く
気が荒い
気のない
気のせい
気の弱い
気の若い
実に多くの表現があります。
日本人なら誰でも何の違和感もなく、日常的に使う日本語です。
こんな日常の日本語「気」に対応する英語が単語としては存在しないのです。
不思議と言えば不思議です。
「気」の英単語はないですが、同じ趣旨のことはすべて英語で表現できます。
take care とかfaintがそうです。
この「気」って、何なのだろうか。なぜ私たちは「気」をこんなに頻繁に使うのでしょうか。
もう一つ例を挙げれば、「こころ」です。「こころ」は心と書く。
心臓の心とすれば、英語ではheartです。英語のheartは臓器以外にも、情緒や感情に深く関わっているという考え方があり、臓器としてのheart以外の意味でも使われます。
しかし、ひらがなで表記した「こころ」は心臓heartと言う意味が全くありません。
以下の表現には日本語独特の「こころ」の意味があるように思います。
「心」の表現を少し列挙してみましょう。
心に浮かぶ
心に描く
心が変わる
心無い
心を奪う
心当たりがある
心を鬼にする
心ある
心ゆくばかり
心を込めて
心の狭い
心の優しい
心ゆくばかり
心から
心ここにない
心の大きい
心に抱く
心を失う
心をひく
実に多くの日常的な表現があり、私たちは何気なく使っています。
「こころ」(心)って、何なんだろう。
“心ここにあらず”の時、私たちは“我を忘れている”ように思います。
すると“こころ”と“我”とが同じなのでしょうか。 “我”は自我、自己、自意識、もう一人の自分、などかもしれません。 でも、頭の働きmindともかなり違うように感じます。
私達日本人は「気」と「心」の定義を考えることはほとんどありません。 私も、昔はさほど気にしたことがありませんでした。
しかし、英語と日本語の対訳をする機会が続くと、時々日英の言葉の違いに不思議さを感じることがあるのです。
日本語にも英語にも、それぞれの長い長い伝統、文化などが独自に内包され、複雑な広がりを持つと感じる次第です。
“忖度”は英語にはない
「忖度」を電子辞書で調べると、guessとsurmiseが出てきます。
guessは易しい言葉で、英語のテキストにも一般のニュースでもよく見ます。
一方、surmiseは滅多に遭遇することがありません。英英辞書を見ると a reasonable guessとあります。
guessは単なる推測、surmiseは合理的な推測とでも言うのでしょうか。
このように「忖度」は英語的には「推測」と同じ意味で、辞書で訳されています。
でも「忖度」は隠れた気持ち、表には出されていない意図など、発言者の内面の心理を推し量るという推量、推察の意味が強いのではないでしょうか。
更に、今回政治の場面でこの言葉が頻繁に取りざたされましたが、日常的には使われることはほとんどない言葉でもあると思います。
guessの使用される頻度とは桁違いに少ない言葉だと思います。
アメリカでは(英語文化では)忖度のような、相手の気持ちを推し量って、それに合わせて、こちらの態度や対応を合わせるということ(文化)があるのでしょうか。
答えは、“ほぼノー”です。
アメリカ人は基本的には(ほとんどの場合は)言葉に表現されたことを文字通り、額面通り理解し、その言葉に適合した対応を取る、即ち忖度しないということが“期待されて”います。
特に、公式に(プライベート以外で)発言されたもの(会社での会議での発言やビジネスの交渉、他人同士の会話など)は、まさしくそうです。
私の体験からも、そのことは推測できます。
もちろんアメリカ人も忖度の気持ちは持っていると思います。親しい友人同士や家族間では、忖度し合ったりしますから、彼らとて人の気持ちが分からないわけではない、というわけです。
ちょっとした表情などを読み取り、言葉で言っていることと、本当の気持ちは違うということは察することができるのです(と思います)。
まあ、人間誰しもそのような“気持ちを察する能力”は持ち合わせていると確信します。
しかし、社会的訓練というか、文化的伝統では、言葉(英語)は発言された通りに額面通りに取るべきである、とされています。
だから、人前や社会的な発言はことさらに慎重に行う意識が強いわけです。
一つ例を考えてみましょう。
国として、アメリカと交渉する立場の日本の場合、安全保障の面、貿易の面などで、「自分たちは弱い立場だから、言いたいことも十分言えない」という心理が働き、アメリカ側に日本の立場を何とか“忖度してほしい”と願う気持ちがあるのではないか、と推測される外交交渉があったりします。
トランプ大統領が日本に不利なことを提案した場合、日本がすぐさま反論しないことはしばしば見られます。彼らの内心では、ちょっと反論(言葉で表現する)してもらえれば、それから「交渉できる」のにと思っていても、日本側が反論しない(言葉に言い表さない)と、賛成したことと理解せざるを得ないという彼らの常識で、対応(反応)しないわけにはいかない、ということになります。
これも「忖度する」と「忖度しない(言葉で表現したものだけをとる)」文化の違いです。
もう少し分かり易い話に例えれば、仮に軍事用戦闘機の交渉を例に考えるとします。
アメリカが一機100億円と価格提示して、日本側に購入を要求してきた場合です。そんな時、日本側は即座に50億でなければ買えない、と反論すべきです。
日本では戦闘機の製造能力がゼロなので、アメリカから買わざるを得ない立場にありますが、価格交渉の時、相手の言い値をそのまま受け入れる必要はない、と考えるべきなのです。(アメリカ人ならそう考えるだろうと思います)
戦闘機って、大量販売はできないものですから、マスプロダクションで製造されるものではありません。ですから、当然コストに対して数倍の利益を上乗せしていると考えられます。100億と言うなら、コストは10か20億ドルだと思われます。
すると100億と提示されたとき、50億とカウンターオファーしてもいいはずです。
そんな時の交渉で、「いやそれは…我が国の予算が厳しくて、そこまでは…いや困りました…上司と相談してみますが…」なんていう対応なら、英語の交渉としては、まったく失格です。
私の言いたいことは、英語の交渉では、カウンターオファーが、“通常の事”だということです。
最後には80億ドルで決着する。最初100億ドルと机を叩いて脅していた相手も喜んで、80億の決着で握手を求めてくることでしょう。アメリカ人の交渉担当者は本国に帰って、「厳しい交渉を乗り越えて、80億ドルで決着できた」と得意げに上司に報告できるはずです。
英語では、言葉で表現されたものを額面通り理解するという伝統(社会的訓練)があるのです。忖度の気持ちというものは個人的、プライベートな感情である、と彼らは捉えていると、私達日本人は考えるべきなのです。
Japan: We will accept the conditions that we have discussed today. Yes, Mr. Smith, we agree with you on the deal.
America: Thank you very much. We came to the reasonable conclusions. It was a very constructive negotiation, Mr. Sato. We’ve enjoyed the meeting. (Shake hands)…
こんな風な終わり方ができれば、英語的な交渉でしょう。
オファー vs カウンターオファー
英語圏での交渉では通常の事です。
ただ、担当者が英語圏の交渉術を熟知していても、忖度の伝統を重んじる国内 の政治家、学者、高級官僚、そして、マスコミなどがそのことを理解していないと、時に非常に難しい立場に立たされることがあります。
「無理に交渉を捻じ曲げている。相手が怒って交渉を中止したらどうするん だ!」
と圧力をかけたりするからです。
あるベテラン担当者はかつて、“後ろから鉄砲の弾が飛んでくる”と愚痴ったこ とがありました。
多くの場合、そんな批判や圧力は交渉当事者を腰砕けにして しまいます。
恐ろしや、忖度!
「思う」vs「think」 を“考える”
「感じる」「思う」「考える」
私はブログの中で、「思う」をよく使います。
「思われる」とか「思える」、「思います」とか、多少バリエーションをきかせて使ったりしますが、「思う」「思う」と頻繁に使っています。
この「思う」と「感じる、感じます」は明らかに違うと“思います”。
でも自分の内なる心の動き(振動、バイブレーション)というか、漂う雰囲気を分析してみると、共通した部分も多いようにも“思う”のです。
一方、「思う」と「考える」はどう違うのでしょうか。
「思う」は精神的作業が弱く、「考える」はその作業が強く、明確であるように“思える”のです。「考える」って、かなり理屈っぽい論理的思考のニュアンスがありそうな“感じ”がしますね。
昔、夏目漱石が小説の中で「知に働けば角が立ち、情に棹させば流される」と書いたことがります。知は“考える”と同じようなものかもしれません。
英語に翻訳すると、次のようになるでしょう。
思う=think、感じる=feel、考える=???やっぱりthinkか。
私の「思う」は「感じる」というニュアンスを少し含んでいそうです。
そして「考える」は「感じる」というニュアンスを全く含んでいないように“思う”のです。
すなわち、私が「思う」と書く時は、「感じる」という心の動きが含まれ、私が「考える」と書く時は、思考は本当に「考える」に特化している、と“思う”のです。
Feel vs Think
私の理解では、I feelは英語ではemotion, emotionalとほぼ同じ意味で、アメリカ人は思考プロセスが含まれない、感覚的な人間感情を表現する時に使う言葉だと‘’思って‘’います。
I thinkはもっと人間の知的な論理的プロセスに基づく思考を表す場合に使う言葉だと‘’思います‘’。
フランスの哲学者デカルトの「我思う、故に我あり」の英訳は、一般的にI think, therefore I am. となります。
日本語では「思う」と訳されていて、英語では thinkになっています。
‘’絶対的な真理を求めて全てを徹底的に疑ってみても、「疑っている自分」の思考だけは排除出来ない‘’
thinking,thoughtは人間が行う特別な心的活動で、人間の本来の姿を現していると考えられているようです。
だからなのか、インテリのアメリカ人は滅多に“I feel”とは言いません。
まあ、emotionalであることが許されているシチュエーション、例えば、家族のことを語るときなどは、I feel、I felt、を使いますが。
仕事の関連で使われることは絶無でしょう(私の知る限りでは)。
「先日テレビで観た映画、良かったですよ」なんていう時、英語では “I think it was a nice movie”.と言うでしょう。
日本語では、“私”(I)は出ていませんが、英語では、I thinkと言うと思います。
この時に、英語で I felt it was a nice movie. と言うか、ですね。
まあ、言えなくはないですが、思考プロセスがきっちり発現されていない、というニュアンスを相手に印象付けてしまうかもしれません。
英語の世界では、思考プロセスがはっきりしているI thinkが圧倒的に好まれるのではないかと‘’思います‘’。
私は「思う」をどうして頻繁にこのブログで使うのかというと、私は自分の考えを読者の方に強く押し付けるつもりはない、あるいは明確な論理的な思考過程を経て物事を語っていないからとも言えます(笑)。
「思う」を頻繁に使う自分の内心をちょっと分析し、英語に絡んで自分を弁明したいと思って、こんな文を書きました。
アメリカで観た映画「七人の侍」
先日NHKのBS放送で、久しぶりに「七人の侍」を観ました。
この映画は1954年公開の映画なので、当時山奥の小さな町の中学生だった私は映画館で観る機会はなく、10年以上たった1965年になってアメリカで初めて観たのです。
留学していた先の大学のキャンパス内のホールで上映されたので、観客はアメリカ人の学生や先生方でした。
映画の評判は私も耳にしていたので、「いい映画らしい」とは思っていましたが、日本映画をアメリカ人と一緒に観るという経験はそれまでになかったので、映画が始まる前は「みんながっかりしたらどうしよう…」という不安もありました。
でも私は映画大好き人間なので、上映が始まったらすっかり映画の世界に引き込まれてしまいましたが…
画面には英語の字幕が出ていて私もつい読んでいたのですが、侍の言葉や百姓(農民)の言葉がこんな風な英語になるのか、と興味をひかれました。
侍は独特の喋り方をしますよね。
それに貧しい百姓と無頼の酒飲みや博打打ちの言葉もそれぞれ違いますが、それら全部が英語としてはごく共通の表現になっていたのが意外でした。
ああ、訳すとこんな風になるのだな…と感じたのを覚えています。
野武士との戦闘で勝利するのがテーマの映画でしたが、その中で若い侍と百姓の娘の淡い恋の駆け引きのシーンがありました。
いつ死ぬかもしれないという緊張の中、若い侍が百姓の娘から無言の誘いを受けドギマギするシーンに、アメリカ人の学生らは大笑いしていました。
日本人の私には侍の恥じらいの心情が手に取るように分かりましたが、アメリカ人にとってはなんともウブで純な様子がすごくかわいらしかったのだろうと思います。
私もつい誘われてアメリカ人と一緒に笑いました。
映画が終わって、周囲のコメントが色々聞こえてきました。
皆とても素晴らしい映画だったと満足しているようでした。
そんな言葉を聞きながら、日本人としてちょっと誇らしい気持ちになったのを覚えています。
この「七人の侍」はアメリカでも評判になり、後に西部劇にリメークされています。
ユル・ブリンナーやスティーブ・マクウィーンが主役を務めた「荒野の七人」です。
この映画がアメリカでとても評価され、有名になった理由はたくさんあると思います。
例えば、侍が単に命令を出す支配者ではなかったこと、農民の総意で野武士との対決を決めたこと、農民の意志が強く表現されていたこと、主役の人々が現代にも通じるような人間味が豊かでそれぞれ個性的であったこと、シーンごとの動きに無駄がなかったこと、迫力のあるダイナミックな戦闘場面があったことなどなど。
全体がある種民主的な合意で敵である野武士に戦いを挑むというテーマも、ユニヴァーサルで文化、伝統の違いを超えて理解しやすかったのではないかと思います。
実に3時間半の大作ですが、私は何度観ても1秒も長いと感じる瞬間はないほど素晴らしい映画です。
これは余談になりますが、アメリカの大学でその他にも映画を見る機会がありましたが、一つ私にとって驚きだったことがあります。
同じ学部の学生らと映画を見て感じたのですが、私は映画が素晴らしければ数時間はその余韻に浸ってしまうクセがあるのですが、他のアメリカ人の学生らはそれがないのです。 映画が終わってその評価や感想をいくつか口にした後は、すぐ翌日の講義の話を始めるし、予習にもとりかかる。さあ勉強だ、みたいに…。
気分転換が恐ろしく速く、あっという間に次のことに頭を切り替える。
まあ、私がちょっと違うタイプということもありますが、それにしてもその気持ちの切り替えの早さには何度も驚かされました。
日本に戻り外資系企業で働いていた頃の外人マネジャーらの気分の転換の速さにも時々驚かされたので、学生だけじゃなくアメリカ人一般の傾向であろう…というのが私の推察です。
このブログを読んでいる方の中で、同じ印象を持たれた方はいるでしょうか??